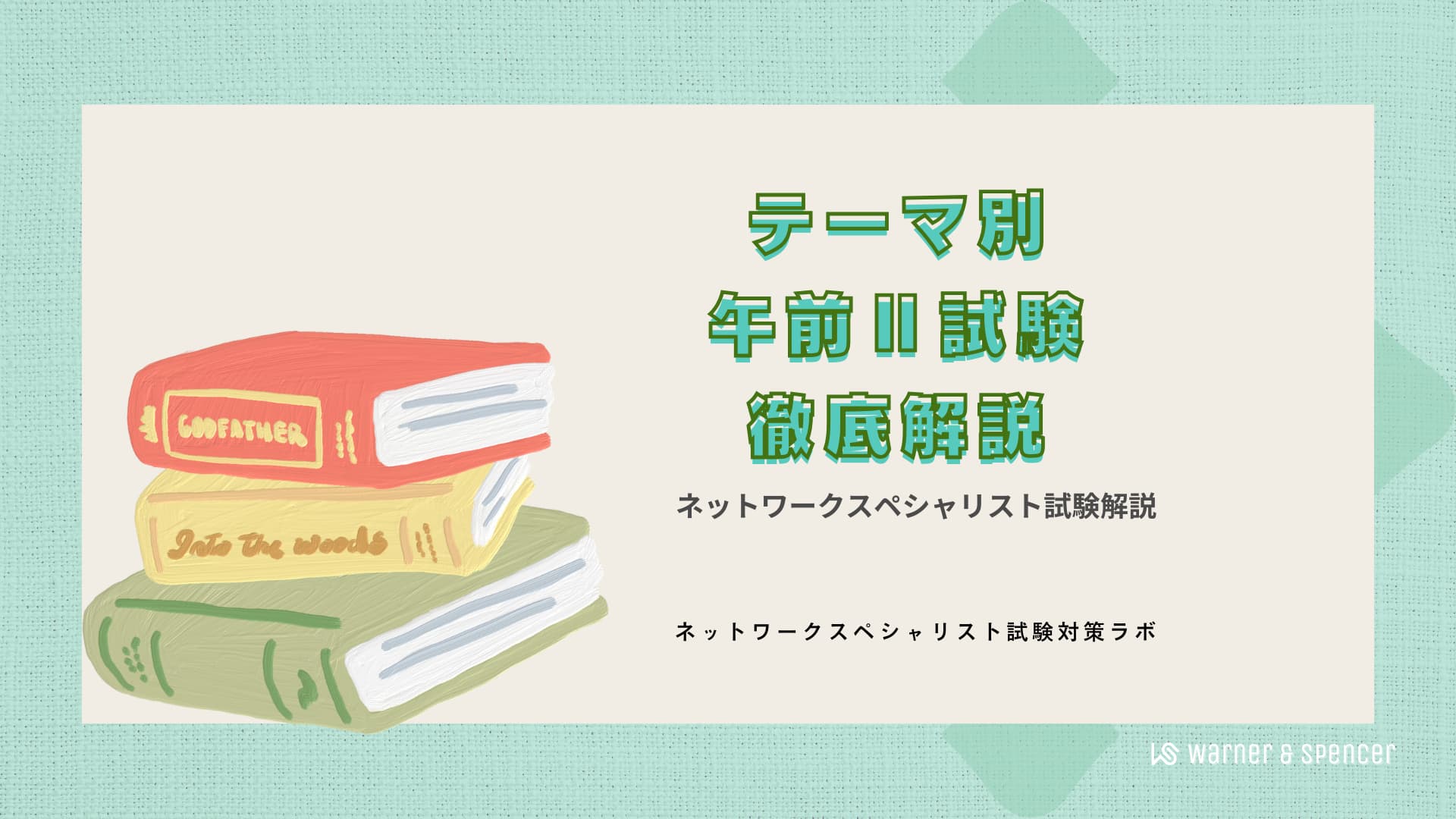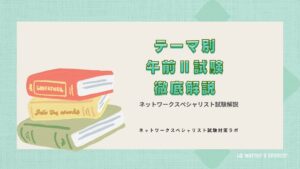目次
問題文
全国に分散しているシステムを構成する機器の保守に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 故障発生時に遠隔保守を実施することによって駆付け時間が不要になり,MTBFは長くなる。
イ 故障発生時に行う機器の修理によって,MTBFは長くなる。
ウ 保守センターを1か所集中から分散配置に変えて駆付け時間を短縮することによって,MTTRは短くなる。
エ 予防保守を実施することによって,MTTRは短くなる。
解説
解答
ウ
この問題は 保守指標(MTBF・MTTR)と保守方式 の正しい関係を理解しているかを確認する出題です。
ア 遠隔保守で駆付け時間が不要になり,MTBFは長くなる
遠隔保守は、現地に技術者が赴かなくてもシステムの診断や復旧を行えるため、駆付け時間を短縮できます。
これにより「故障発生から復旧までの時間」を削減でき、運用上の効率化に大きく寄与します。
ただし、影響を受けるのは修理時間の指標であるMTTRであり、MTBFのように機器そのものの信頼性を直接高める効果はありません。
イ 機器の修理によって,MTBFは長くなる
修理は機器が故障した後に行われる行為であり、再び利用可能な状態へと戻すものです。
つまり修理によって改善されるのは「修理に要する時間」の部分であり、機器が次に故障するまでの稼働時間=MTBFを直接延ばすことにはつながりません。
MTBFは設計や部品寿命に依存するため、修理活動とは別の指標として考える必要があります。
ウ 保守センターを集中から分散配置に変えて駆付け時間を短縮することで,MTTRは短くなる
全国規模でシステムを展開している場合、保守センターを1か所に集中させると現場到着までに長時間を要することがあります。
拠点を分散配置すれば、地理的に近い場所から駆け付けられるため、修理開始までの時間を効果的に削減できます。
これにより、平均修理時間=MTTRを短くでき、システム全体の稼働率向上にも寄与します。
大規模システムでは一般的に採られる改善策の一つです。
エ 予防保守を実施することによって,MTTRは短くなる
予防保守は、故障が発生する前に部品交換や点検を行うことで、障害の発生頻度を減らし、結果的に平均故障間隔=MTBFを延ばす取り組みです。
これによりシステムの停止リスクを下げられますが、修理そのものに要する時間(MTTR)を短縮する仕組みではありません。
MTBFとMTTRは役割が異なる指標であるため、予防保守は「故障までの間隔」を伸ばす活動と整理すべきです。