今回はWi-Fi環境下などで通信の衝突を避けるために使われるCSMA/CAという通信プロトコルについて学習します。

また難しそうな単語が出てきましたね……。



学習に入る前に、半二重通信と全二重通信について復習をしてもらえるとスムーズです。
半二重通信とはデータの送信と受信を交互に行う方式で、一度に一方向しか通信できません。一方、全二重通信は送信と受信を同時に行える方式です。
無線でのネットワークが一般的となった現代において、通信の衝突を避けるためのCSMA/CAの技術は必ず押さえておきたい知識です。
少し難しくなりますが、頑張って学習していきましょう!
CSMA/CAとは
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) とは、ネットワークでデータの衝突を回避するための通信プロトコルです。(最後のAは回避という意味です)
主に無線ネットワークで使用されており(※)、Wi-Fiのような環境で効率的にデータを送信するために利用されています。
※CSMA/CAは有線ネットワークの一部でも使用されることがあります。例えば、無線と有線の混在環境での衝突回避に利用される場合があります。
無線通信は、複数の端末が同時に通信できないため半二重通信となります。つまり、一度に一方向にしか通信ができない仕組みです。
このため、送信と受信を交互に行う必要があり、通信効率が制約されることがあります。
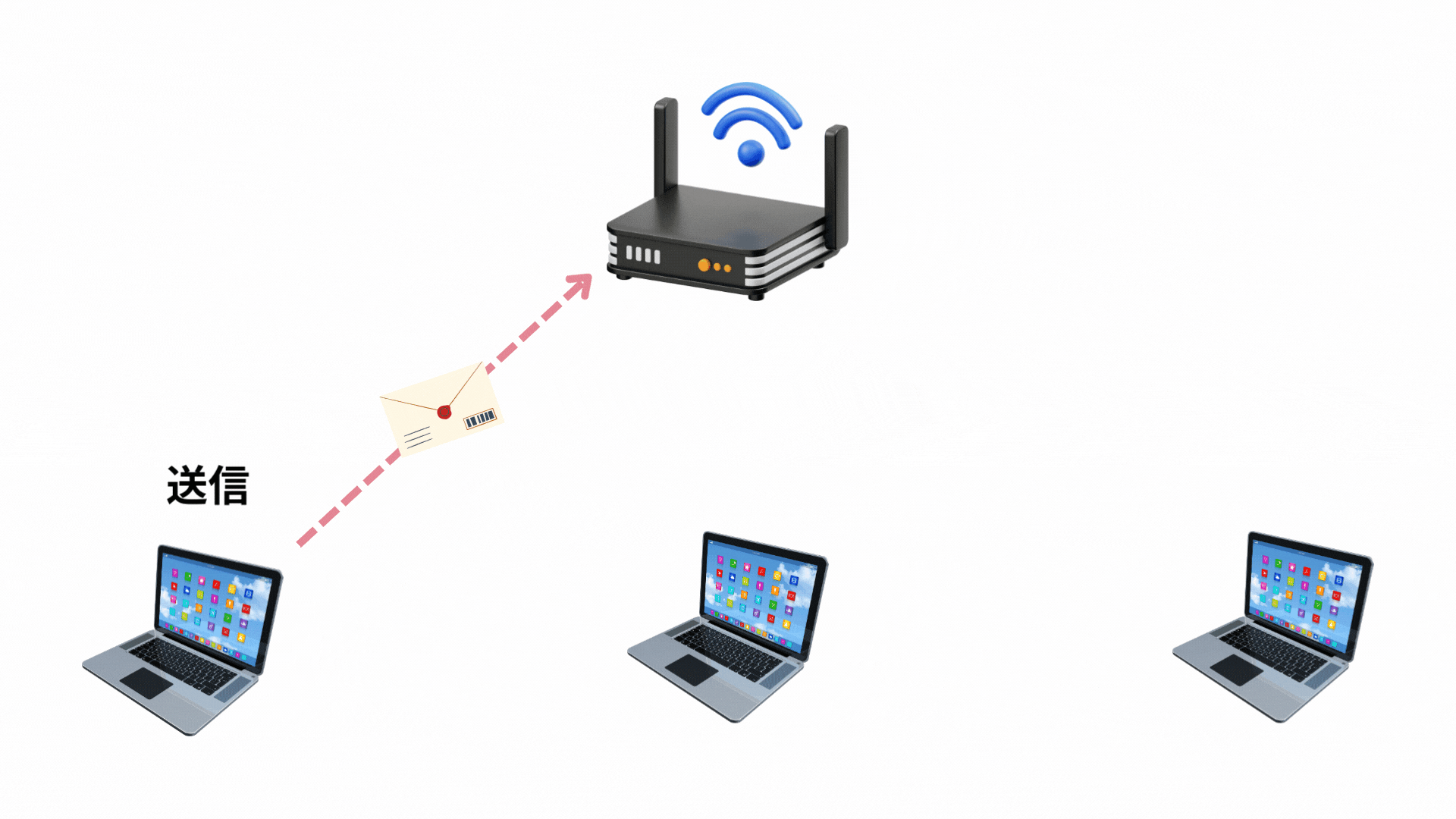
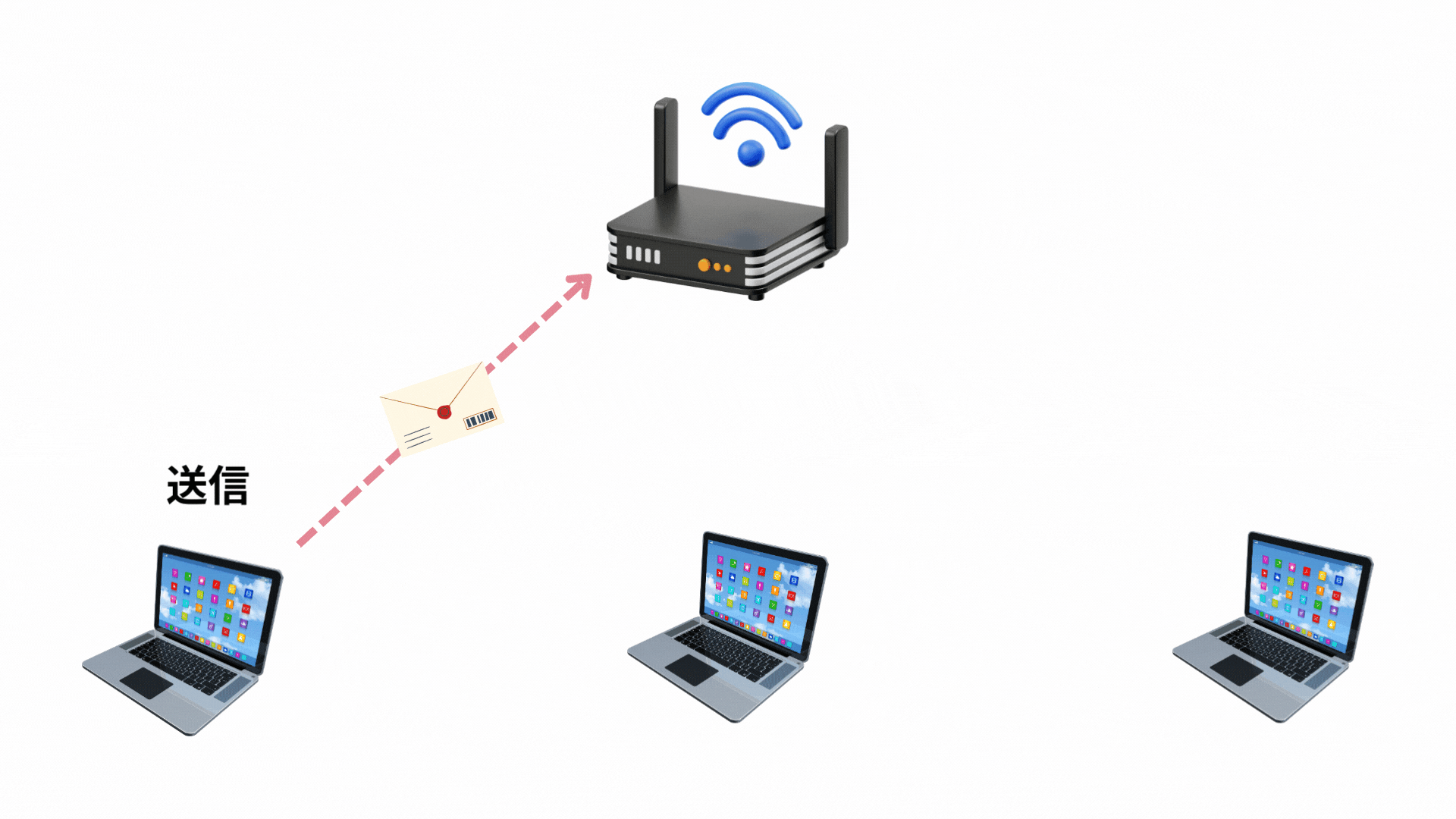
かつては有線ネットワークでも半二重通信が行われており、その際にはCSMA/CD(最後のDは検知:デテクション)が採用されていました。
CSMA/CDは衝突を検知した後にデータを再送する仕組みで、交通事故が発生したらもう一度送り直すイメージです。
この方式では、データの送信中に衝突が発生すると、その衝突を検知してからデータの再送が行われます。



有線環境での衝突は検知可能であったため、このプロトコルは当時非常に有効でした。
一方、無線ネットワークではCSMA/CAが使用されます。
無線通信では電波の特性上、衝突を検出するのが難しいため、最初から衝突が起きないように回避することが重要なのです。
具体的には、送信前にチャネルの状態を確認し、もしチャネルが使用中であれば送信を遅らせる仕組みを使います。
このように、衝突を未然に防ぐための「回避」プロセスがCSMA/CAの中心です。
Wi-Fiのような環境で効率的にデータを送信するために利用されており、特に混雑した環境でその効果を発揮します。
たとえば、オフィスや公共の場など、複数の端末が同時にアクセスする状況では、CSMA/CAの衝突回避機能がネットワークの安定性と効率性を維持するために重要な役割を果たします。


無線環境では信号の衝突が発生するとデータが失われる可能性が高いため、衝突を防ぐための工夫が非常に重要です。
このため、無線ネットワークでは、衝突が発生しないようにするためにチャネルの監視や待機時間の導入などのさまざまな技術が使用されています。
CSMA/CAはこうした環境で、複数の端末が効率的に通信できるように設計されています。
衝突が発生するとデータの再送が必要となり、これにより遅延が発生する可能性があるため、あらかじめ衝突を防ぐ設計が重要となるのです。
通信の流れ
CSMA/CAの動作原理について詳しく説明すると、まず送信機はデータを送信する前に通信チャネルが使用中かどうかを確認します。このプロセスを”キャリアセンス”と呼びます(Cが搬送波、Sが検知でCS)。
※搬送波は常に一定の周波数で流れている波で、これを「キャリア(搬送)」としてデータを送信する際に利用します。
搬送波が流れていることで、無線通信を行う際に「今、データを送信しているかどうか」を他の端末が検知できるようになります。つまり、搬送波が途切れることなく流れているため、データを送受信するタイミングで、その波に変調をかけて情報を送ることが可能です。
通信を始める前に、まず搬送波の状態を確認し、誰もデータを送信していなければ、自分のデータを送信するという仕組みで動作します。


チャネルが空いていることを確認できた場合、送信機はデータを送信します。
その際、衝突を避けるためにランダムな待機時間(バックオフ制御時間)を設定します。


これにより、他の端末と同時に送信を試みて衝突が発生する可能性を減らすことができます。
このバックオフ制御時間は、各端末が異なるランダムな時間を待つことで、同時に送信を行う可能性を低くする役割を果たしています。



他にも待っている端末があった場合、同じタイミングで通信を送っちゃうかもしれないですもんね。
バックオフ制御時間の設定後、送信機はデータの送信を開始します。
データが送信されると、アクセスポイント(AP)はそのデータを受信し、問題なく受信できた場合には送信元の端末に対してACK(確認応答)を送信します。


このACKは、データが無事に相手に届いたことを示すものであり、送信元の端末にとって非常に重要な役割を担っています。
もし一定時間内にACKが返ってこない場合は、通信に障害が発生したとみなして再送を試みます。



この再送のプロセスは、通信が確実に成功するようにするための重要な手順であり、信頼性を高めるための仕組みです。
ACKを受信した端末は、次のデータ送信を行う前に再びランダムな待機時間(バックオフ制御時間)を待ちます。



こうして毎回ランダム秒待つのは無駄なような気もしますが、通信の衝突を避けるためには重要なのですね。



そうです。バックオフ制御時間の重要性は、きちんと理解しておきたいところですね。
このバックオフ制御は、無線通信の安定化において非常に重要な要素であり、特に複数の端末が頻繁にアクセスする環境でその効果を発揮します。
さらに、CSMA/CAは効率的な通信を行うために、RTS/CTS(リクエスト・トゥ・センド/クリア・トゥ・センド)といったハンドシェイクプロトコルを用いることもあります。
※ハンドシェイクプロトコルとは、通信においてデータを送信する前に、送信元と受信先が互いに準備ができていることを確認するための手順のことです。
これは、通信の開始前に双方が意思疎通を行うことで、データの送信が円滑に進むようにするものです。
このRTS/CTSは、特にネットワークが混雑している場合に有効であり、送信の競合を減らすための追加の手順です。
RTSは送信リクエストを意味し、送信機がAPに対して「これからデータを送信したい」というリクエストを送ります。
一方、APがこれに対して「送信しても良い」という応答をCTSで返すことで、他の端末が同じタイミングで送信することを防ぐことができます。
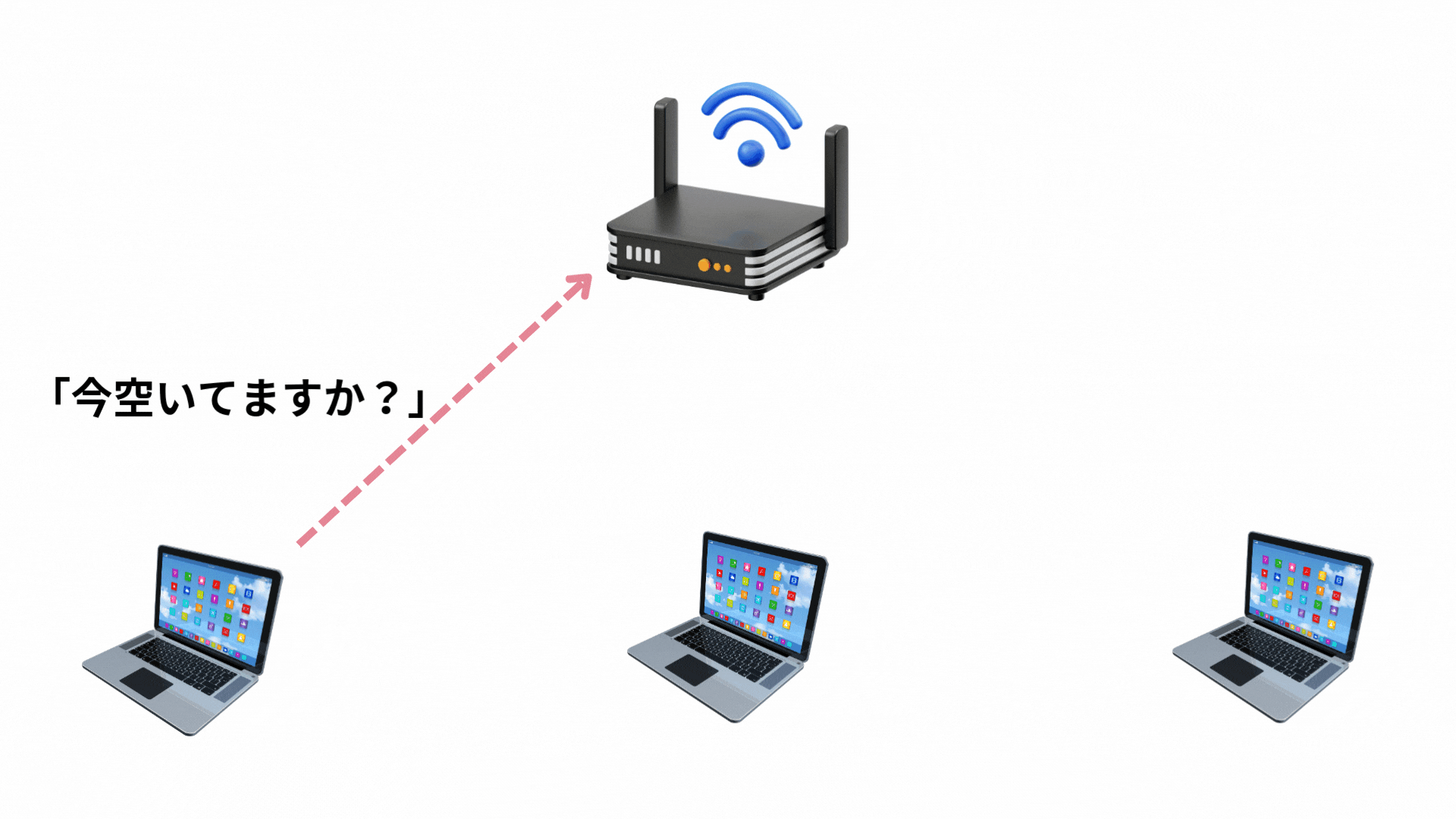
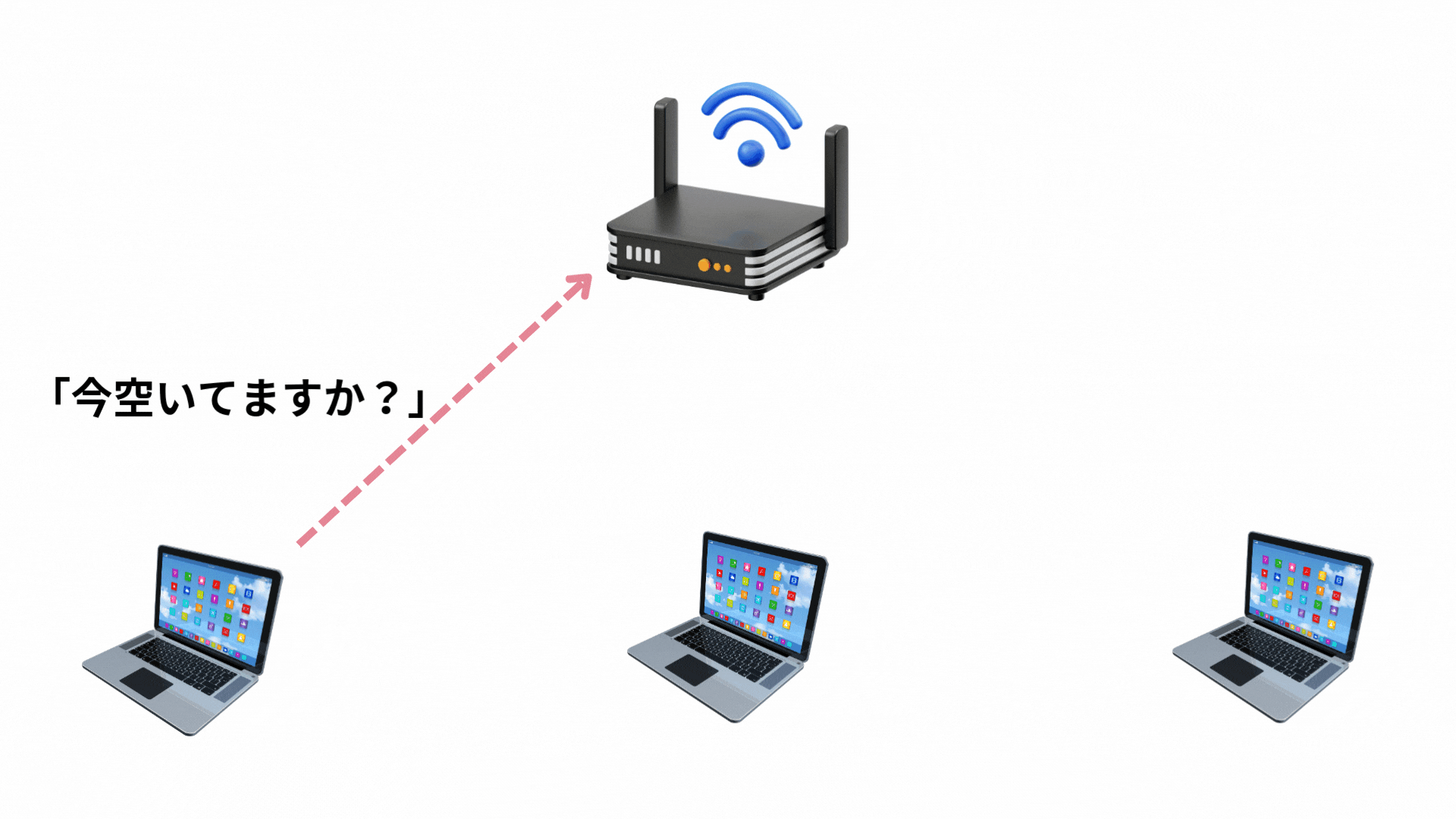
RTS/CTSを利用することで、送信の衝突を未然に防ぎ、データの正確な受け渡しが保証されるのです。
この仕組みは、特に大量の端末がネットワークに接続している状況下で有効であり、ネットワーク全体のパフォーマンスを維持する上で重要な役割を果たします。
例えば、大規模なイベント会場やオフィス環境など、複数のユーザーが同時にアクセスする場面では、このプロトコルがネットワークの効率的な運用を支える要素となります。
また、無線通信の特性上、電波は周囲の障害物や他の信号の影響を受けやすいため、CSMA/CAのような衝突回避機能は特に重要です。



2.4GHz帯の電波は、たとえば電子レンジの電磁波に影響されやすいんですよ。



わ、ほんとに他の信号の影響を受けやすいんですね。
これにより、通信の信頼性が確保され、利用者がスムーズにデータを送受信できる環境が提供されます。
データの衝突や再送が頻発すると、通信の遅延やネットワークの混雑が発生するため、CSMA/CAの仕組みはこれを防ぐための基盤として機能しています。
このように、CSMA/CAは無線ネットワークにおけるデータの衝突を防ぎ、効率的な通信を可能にするために設計されたプロトコルです。
その中でもキャリアセンス、バックオフ制御時間、ACKの確認、RTS/CTSハンドシェイクといった一連のプロセスが、ネットワークの安定した運用を支えています。
アドホックモードとインフラストラクチャモード
無線ネットワークには、主に「アドホックモード」と「インフラストラクチャモード」という二つの運用形態があります。ネットワーク設計や運用において、それぞれのモードについて理解することが大切です。
アドホックモードは、アクセスポイント(AP)を使用せずに、端末同士が直接通信を行う形態です。
このモードは、臨時にネットワークを構築する場合や、少数の端末間で簡単にデータを共有したいときに利用されます。
例えば、会議室で参加者が自分の端末を使って一時的にネットワークを形成する際に有効です。
また、アウトドアでのイベントや災害時の緊急連絡など、迅速にネットワークを構築したい場合にも役立ちます。
アドホックモードは、設置が容易であり柔軟にネットワークを構築できますが、端末が増えると通信の管理が難しくなるというデメリットがあります。
このため、大規模なネットワークにはあまり向いておらず、小規模での一時的な利用に適しています。
一方、インフラストラクチャモードは、アクセスポイント(AP)を中心にして端末が通信を行う形態です。
このモードでは、すべての端末がAPを介してデータを送受信するため、ネットワークの管理や制御が容易です。
また、複数のAPを利用することで、広範囲にわたるネットワークの構築が可能となります。
例えば、大規模なオフィスビルや商業施設、学校などで複数のAPを配置し、広いエリアで安定したネットワーク接続を提供することができます。
このため、オフィスや家庭、公共の場でのWi-Fiネットワークなど、恒常的に安定した通信が求められる環境で広く利用されています。
インフラストラクチャモードでは、セキュリティ機能の導入も容易であり、ネットワーク管理者がアクセス制御を行うことができる点も大きなメリットです。
アドホックモードとインフラストラクチャモードの違いを理解することで、無線ネットワークの特性を活かし、適切な環境で適切なモードを選択することが可能になります。
まとめ
今回の記事では、無線ネットワークで使用されるCSMA/CAプロトコルについて詳しく解説しました。
CSMA/CAは、無線環境でのデータの衝突を未然に防ぎ、効率的に通信を行うために設計された重要なプロトコルです。
その動作原理として、キャリアセンス、バックオフ制御、ACKの確認、そしてRTS/CTSハンドシェイクといった一連の手順が、ネットワークの安定した運用を支えています。
無線ネットワークは、建物の障害物や複数の端末の存在によって、衝突や効率低下といった問題が発生しやすい環境です。
しかし、CSMA/CAのようなプロトコルとRTS/CTSといった仕組みを活用することで、これらの課題に対処し、ネットワークの信頼性と効率を向上させることが可能です。
ネットワークスペシャリスト試験に向けて、これらの知識をしっかりと理解し、実際の応用にも役立ててください。







