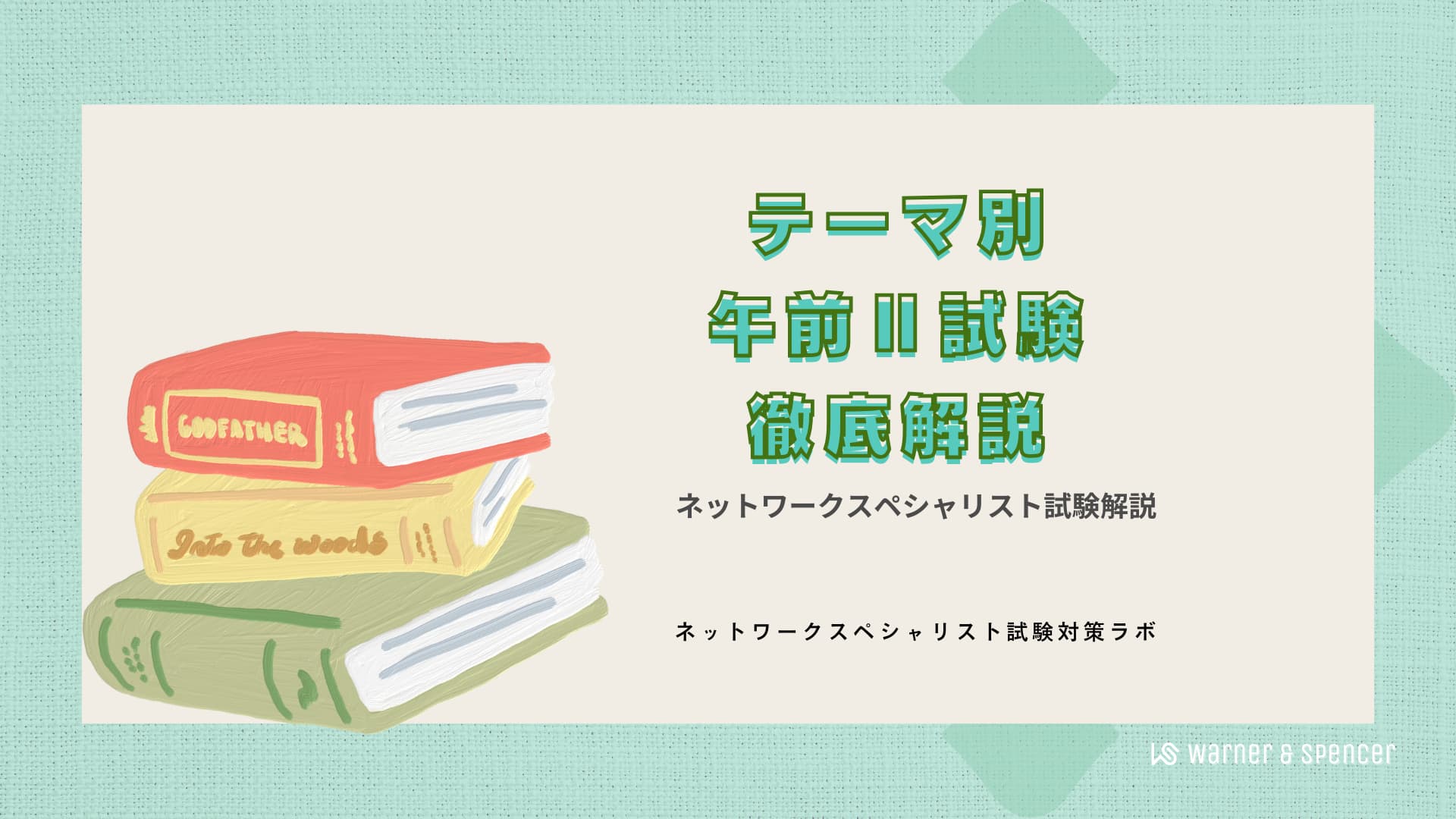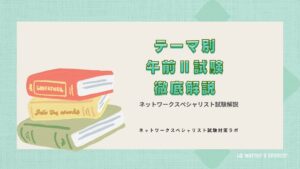目次
問題文
ストレージ技術におけるシンプロビジョニングの説明として,適切なものはどれか。
ア 同じデータを複数台のハードディスクに書き込み,冗長化する。
イ 一つのハードディスクを,OSをインストールする領域とデータを保存する領域とに分割する。
ウ ファイバチャネルなどを用いてストレージをネットワーク化する。
エ 利用者の要求に対して仮想ボリュームを提供し,物理ディスクは実際の使用量に応じて割り当てる。
解説
解答
エ
この問題は「ストレージ技術におけるシンプロビジョニング(Thin Provisioning)」の特徴を問うものです。似ている用語(RAID、パーティション、SANなど)との違いを意識すると整理しやすいです。
ア 同じデータを複数台のハードディスクに書き込み,冗長化する
これは RAID1(ミラーリング) の説明です。
冗長性を高め、1台のディスクが故障してもデータを失わないようにする仕組みです。
可用性向上には有効ですが、シンプロビジョニングのような「仮想ボリュームの柔軟な割り当て」には関係しません。
イ 一つのハードディスクをOS領域とデータ領域に分割する
これは パーティショニング の説明です。
1台の物理ディスクを複数の論理領域に分割して使いやすくする方法で、古くから利用されています。
ただし、事前に固定的に割り当てるため、利用状況に応じて柔軟に容量を節約することはできません。
ウ ファイバチャネルなどを用いてストレージをネットワーク化する
これは SAN(Storage Area Network) の説明です。
ストレージをサーバから独立させ、専用ネットワークを介して接続することで、拡張性や高速性を確保する方式です。
これもインフラ構成の技術であり、プロビジョニングの考え方そのものを説明したものではありません。
エ 利用者の要求に対して仮想ボリュームを提供し,物理ディスクは実際の使用量に応じて割り当てる
これが シンプロビジョニング(Thin Provisioning) の説明です。
ユーザには大容量の論理ボリュームを割り当てたように見せつつ、物理的なディスク領域は実際にデータが書き込まれた分だけ消費されます。
これにより、ストレージ資源を効率よく利用でき、容量の無駄を大幅に削減可能です。
さらに、運用上は「将来の利用を見越した大きな領域を論理的に先に与える」ことで、柔軟な拡張を可能にするという利点もあります。