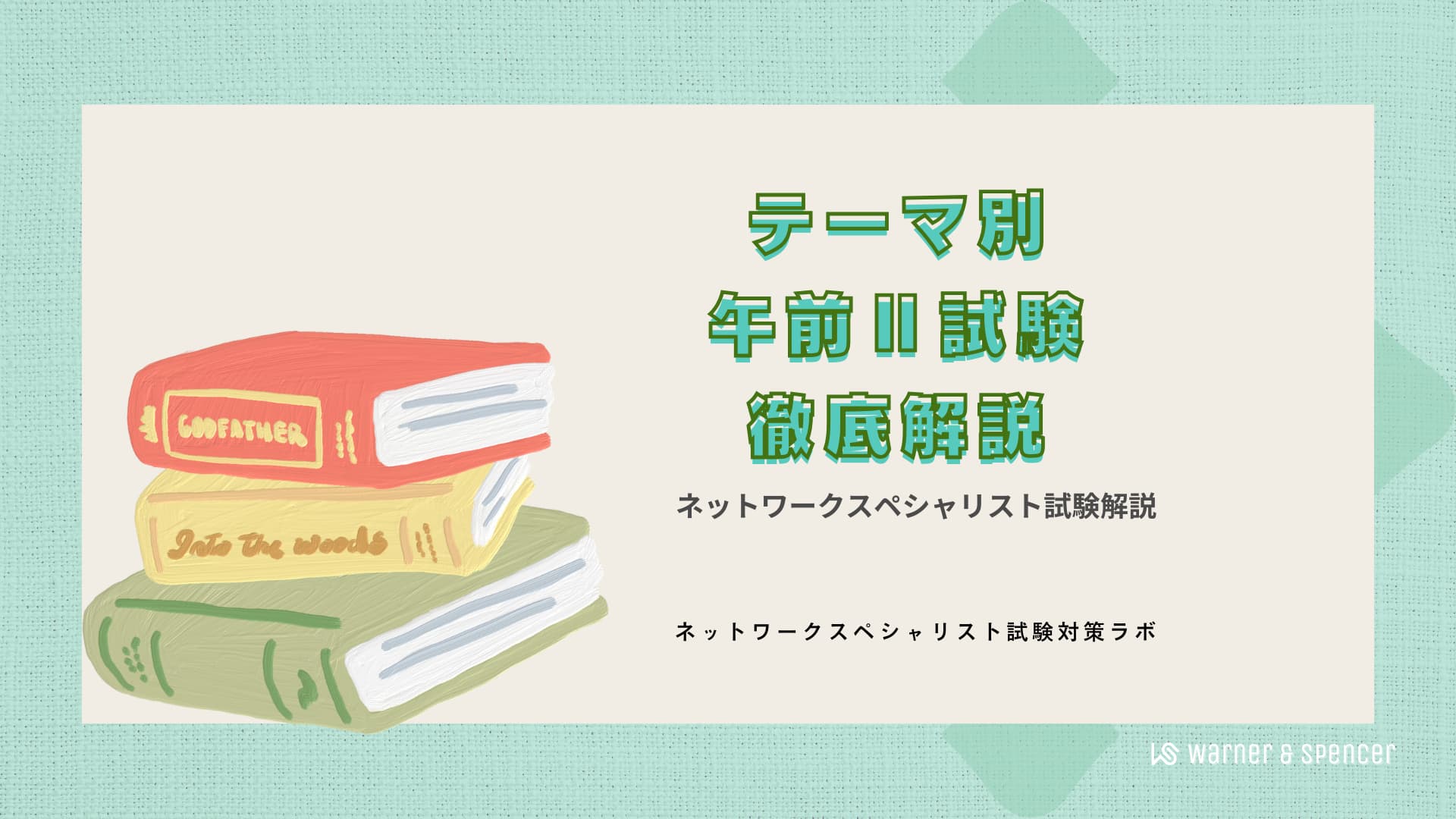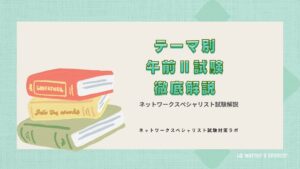問題文
信頼性工学の視点で行うシステム設計において,発生し得る障害の原因を分析する手法であるFTAの説明はどれか。
ア システムの構成品目の故障モードに着目して,故障の推定原因を列挙し,システムへの影響を評価することによって,システムの信頼性を定性的に分析する。
イ 障害と,その中間的な原因から基本的な原因までの全てを列挙し,それらをゲート(論理を表す図記号)で関連付けた樹形図で表す。
ウ 障害に関するデータを収集し,原因についてなぜなぜ分析を行い,根本原因を明らかにする。
エ 多角的で,互いに重ならないように定義したODC属性に従って障害を分類し,どの分類に障害が集中しているかを調べる。
解説
イ
この問題は、FTA(Fault Tree Analysis:故障の木解析)の特徴を正しく理解しているかを問うものです。
FTAは、システムのトップレベルの障害(トップ事象)から出発し、その障害が起きる原因を論理的に分解し、樹形図(Fault Tree)として表現する手法です。
各原因や中間事象は論理ゲート(AND、ORなど)で関連付けられ、障害発生のパターンを分析します。定性的な分析だけでなく、原因の確率を用いて定量的な評価を行うことも可能です。
ア:FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)の説明
FMEAは、システムや製品の構成要素ごとに「どのように壊れる可能性があるか(故障モード)」を洗い出し、それぞれの故障が全体の機能や安全性にどのような影響を与えるかを分析する手法です。
主に設計段階で使用され、故障の発生頻度や影響の重大さ、検出のしやすさを評価して、優先的に対策すべき部分を明らかにします。
定性的な分析が中心ですが、スコア化してリスク順位を付けることもあります。
イ:FTA(Fault Tree Analysis)の説明【正解】
FTAは、トップ事象(起きてほしくない障害)から出発し、その原因を段階的に分解していくトップダウン型の分析手法です。
原因と結果の関係は「ANDゲート」や「ORゲート」といった論理記号でつなぎ、樹形図として可視化します。
これにより、障害発生の論理的なパターンや、どの要因が障害に直結しているかを整理できます。定性的分析だけでなく、各原因の発生確率を用いた定量的評価も可能です。
ウ:なぜなぜ分析(Why-Why Analysis)の説明
なぜなぜ分析は、発生した問題に対して「なぜ?」を繰り返し問いかけることで、根本原因を掘り下げる手法です。
多くの場合は5回程度「なぜ?」を繰り返して、表面的な原因ではなく真の原因にたどり着きます。
製造業や品質管理、トラブルシューティングなど、幅広い分野で利用されています。
FTAやFMEAのような図式化は必須ではなく、文章ベースでの記録が多いです。
エ:ODC(Orthogonal Defect Classification)の説明
ODCは、ソフトウェアやシステムの障害を複数の観点(機能・タイミング・影響範囲など)で分類し、どの属性に障害が集中しているかを分析する手法です。
「直交(Orthogonal)」という言葉の通り、分類基準は重ならないように定義されます。
これにより、障害の傾向を客観的に把握し、改善の優先度を決めやすくなります。ソフトウェア開発プロセスの改善にもよく使われます。